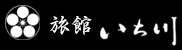- トップ
- いち川の歴史
いち川の歴史

400年の旅路
創業400年 日本最古の旅籠『角屋』
- 徳川家3代将軍・徳川家光の頃──。
江戸(幕府)と京(朝廷)を結ぶ中山道六十九次のうち、
江戸から数えて46番目の大井(現・恵那市)の宿場にて、
初代・市川左右衛門が旅籠『角屋』の営業を始めました。
武家のみならず、庶民も「旅」を許される時代が到来するや、多くの人々が宿場町を行き交い、
とりわけ、大井宿は京に向かう中山道と、尾張・伊勢への道の分岐点にも近く、
お伊勢さんや善光寺への参拝客、尾張商人などで大いに賑わったのです。
幕末、皇女和宮が14代将軍家茂に輿入れするための降嫁行列が東に下った時の騒ぎは大変なもので、
中山道が「姫街道」と呼ばれる由縁ともなりました。
その後、江戸の時代は幕を閉じ、宿場もその役割を終え、
全国の旅籠もわずかに残るだけとなる中、
『角屋』は、明治初年に『旅館いち川』と名を改めながらも、
旅館の風情、日本の心をそのままに、最も古い旅籠として営業を続けて参りました。
「道があるから 人が出逢う」
- 今日も、これからも、
『角屋』は国内の、また海外の人々の喜びの交差点でありたいと願っております──。
いち川のなりたち
 当家初代市川左右衛門は寛永年代旅籠屋「角屋」を現在地にて始めました。
当家初代市川左右衛門は寛永年代旅籠屋「角屋」を現在地にて始めました。
爾来400年地域の皆様方のご支援のお陰をもって、
今日まで営業を続けて来ることが出来ました。
角屋の屋号も明治初年に「旅館いち川」に更めております。
建物は天明7年の大井宿大火の後、再建され、
玄関ロビーに掲げてあります写真にあるものが、昭和10年迄続いて参りました。
木曽路特有の出格子二階建ての建物で、右方に高費用の立派な門がありました。
江戸方から来て3つめの枡型のつき当たりに東を向いて建っていました。
それで『角屋』と申しました。 私の父が昭和初期から終戦前まで20年間、大井町長をやっていまして、
私の父が昭和初期から終戦前まで20年間、大井町長をやっていまして、
その間、桝形道路は不便であるということで、
市川家と隣の古屋家の所有地を提供して、
大井橋まで直線の道路を昭和10年に開通しました。
誠に残念でしたが、古い角屋の建物は全部取り壊しとなり、
現在の建物はそれ以後のものばかりとなりました。
庭にあります、赤松と錦松は昔からあるものですが、
古いことを全て知っているわけですが、
それを聞くすべもございません。
当家14代 市川信平記す
旅籠屋とは
 旅籠屋「角屋」旅籠屋とは、江戸時代旅人を泊め食事を供することを業とした家をいいます。
旅籠屋「角屋」旅籠屋とは、江戸時代旅人を泊め食事を供することを業とした家をいいます。
江戸時代の街道には宿場ごとに多くの旅籠屋があり、
武士や一般庶民の泊り客で賑わいました。
大井宿は、中山道屈指の宿場町で旅籠屋も多く、
天保14年(1843)で41軒でした。
これは美濃16宿中最高です。
中山道各宿の平均旅籠数が27.1軒ですから、
大井宿のにぎわいが想像できます。 「旅館いち川」上の写真は大井宿の旅籠屋「角屋」の正面ですが、
「旅館いち川」上の写真は大井宿の旅籠屋「角屋」の正面ですが、
木曽路に多い出桁造となり、取外しのできる格子戸がはまり、
軒には講札が多くかけてあります。
その右側は特殊な方の出入り門となっていました。
角屋(現・旅館いち川)は建物こそ新しくなっていますが、
現在も江戸時代の代表的な旅籠屋を大井宿中唯一続けています。